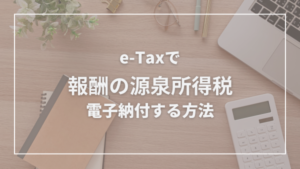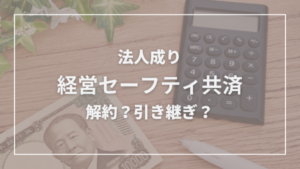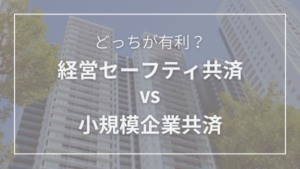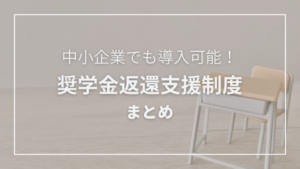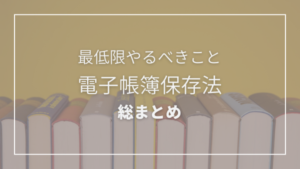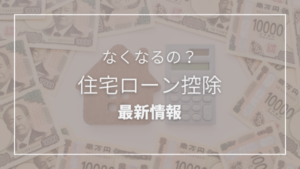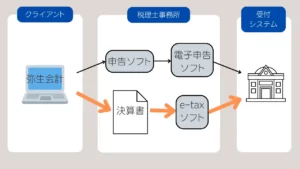- 確定申告を間違えたら税務署から連絡が来るのか気になる
- 突然、税務調査がくるのか不安
- 確定申告の間違いを修正する方法を知りたい
確定申告の間違いに気がついた場合、税務署から連絡が来るのか不安になりますよね。
確定申告の間違いが指摘されるかどうかは、ケースによって異なります。
中には、間違いがあっても税務署から何も連絡がないこともあります。
ですが、放置するとペナルティが増えるため注意が必要です。
本記事では、確定申告の間違いが指摘されるケースや連絡がこないケースから、間違えたときの対応方法まで詳しく紹介します。
この記事で確定申告間違いの不安を解消し、ミスをしても正しく対応できる方法を確認しましょう。
当事務所のサービスメニュー
確定申告間違いで連絡がくるとき・こないとき
確定申告の内容は税務署でチェックされ、必要に応じて連絡がくることがあります。ただし、すべての間違いに連絡があるわけではなく、内容によって対応が異なります。
- 簡単な計算間違いや記載漏れはすぐに連絡がくる
- 税務調査は事前に連絡がくる
- 税金を払いすぎても連絡はこない
- 間違いがあっても指摘されないこともある
順番に解説します。
簡単な計算間違いや記載漏れはすぐに連絡がくる
簡単な計算間違いや記載漏れは、税務署が申告内容を確認した時点で比較的早く連絡が来ることがあります。
たとえば、以下のようなケースです。
- 確定申告書と添付書類の数字が異なる
- 還付口座の記載が抜けている
- 端数処理のミスや計算間違いがある
多くの場合は電話で確認があり、その場で修正を求められます。連絡が来たら、指示に従って速やかに対応しましょう。
税務調査は事前に連絡がくる
基本的に税務調査時は税務署から事前に連絡があり、その後調査が実施される仕組みです。
早ければ確定申告期限が過ぎた4月頃から、確定申告書に記載された電話番号に連絡が来ます。
ただし、以下のようなケースでは、事前通知なしで調査がおこなわれることもあります。
- 連絡が取れない場合
- 悪質な所得隠しや虚偽申告の疑いがある場合
- 現金取引が多い業種(飲食業、小売業など)
税務調査は基本的に拒否できませんが、都合がつかない場合は税務署と相談して日程の調整が可能です。
税務署から連絡があった際は、無視せずきちんと対応しましょう。
税金を払いすぎても連絡はこない
確定申告で誤って本来より多く納税しても、税務署から連絡が来ることは基本的にありません。
税務調査は納税額が少ないと疑われるケースにおこなわれるため、払いすぎた場合は基本的に指摘しません。そのため、自分で気づいて手続きをしない限り、税金は戻ってこないのです。
払いすぎた税金を取り戻す手続き方法は、「申告期限「後」に払いすぎていたら「更正の請求」」で詳しく解説します。あわせてご覧ください。
確定申告は手続きが煩雑で、申告直後はミスに気づきにくいものです。数日後に改めて見直すと、間違いに気づくことができます。
- 必要な経費を計上し忘れてないか
- 計算ミスをしていないか
- 社会保険料や生命保険料は正しく入力されているか
- 医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除など控除漏れがないか
- 配偶者の年収や扶養親族の情報に間違いがないか、など
確定申告後は早めに見直し、払いすぎを防ぎましょう。
間違いがあってもすぐに指摘されないこともある
確定申告に間違いがあっても、すべてのミスがすぐに指摘されるわけではありません。
経費の計上ミスや一部の控除漏れなどは、申告書の記載内容だけでは判断できないためです。
間違いが見つかるのは、確定申告書以外の資料と照合や分析がおこなわれた後です。
以下のような情報をもとに、税務署がチェックをおこなう可能性があります。
- 取引先の支払調書
- 銀行口座の入出金履歴
- 証券口座の取引履歴
- 不動産の登記情報
これらのデータを総合的に分析し、申告内容に不審な点があると判断された場合は税務調査へと進みます。
「指摘されない=問題がない」わけではありません。数年後に税務調査の対象になる可能性もあります。
最近ではAIを活用した税務チェックが導入され、申告漏れが発生しやすいケースを重点的に調査するようになりました。
後で間違いが発覚すると修正申告や追徴課税のリスクが生じます。そのため、税務署から指摘がなくても、申告内容にミスがあれば自主的な修正をおすすめします。
確定申告間違いに気づいたら?ケース別4つの対応方法
確定申告でミスに気づいた場合、間違いの種類や申告のタイミングによって、適切な対応方法が異なります。
- 税金が変わらないなら「電話連絡」
- 確定申告期限「内」は再提出する
- 申告期限「後」に払いすぎていたら「更正の請求」
- 申告期限「後」に少なく払っていたら「修正申告」
順番にみていきましょう。
税金が変わらないなら「電話連絡」
確定申告の内容に誤りがあっても、税額に影響がない場合は、税務署へ電話連絡をするだけで修正できることがあります。
たとえば、以下のようなケースでは税務署に電話連絡し、指示に従って対応すれば問題ありません。
- 住所や家族の生年月日などの記載ミス
- 誤った税務署にe-Taxを送信
- 還付口座の記載漏れ
- 添付書類の不備(追加提出で対応可能な場合)
過去に誤った税務署へe-Taxを送信したことがありますが、税務署に電話連絡をしたところ、正しい税務署へ転送手続きをしてもらえました。また、還付口座の記載漏れも、電話だけで対応が完了し、再提出は不要でした。
このように、税金の金額が変わらないミスは、税務署へ電話をすれば職員が修正や適切な手続きを案内してくれるため、早めの電話連絡がおすすめです。
確定申告期限「内」は再提出する
確定申告の提出期限内に間違いがわかれば、何度でも訂正して再提出が可能です。複数回提出しても、最新のものが正式な申告として扱われます。税務署への連絡や来所も不要です。
申告期限内に修正すればペナルティも発生しないため、間違いに気づいたら早めに再提出しましょう。
- 所得税および復興特別所得税:3月15日まで
- 贈与税:3月15日まで
- 消費税および地方消費税:3月31日まで
確定申告の再提出は、e-Taxまたは書面で提出可能です。
基本的には、最初と同じ手順で訂正した申告書を作成し、提出すれば問題ありません。訂正部分だけでなく全帳票を再提出しましょう。添付書類をすでに提出している場合は、再度提出する必要はありません。
ただし、すでに還付金を受け取っている場合は、すでに受け取った還付金との精算(納付)が必要になるため、注意が必要です。
- 還付金額が少なくなる
- 納付する税金が発生する
このような場合は、事前に税務署へ相談してから再提出しましょう。
申告期限「後」に払いすぎていたら「更正の請求」
確定申告期限後に税金を払いすぎていると気づいたら、「更正(こうせい)の請求」手続きで正しい税額に修正し、払いすぎた分を取り戻せます。
たとえば、以下のような間違いに気づいた場合です。
- 経費を一部入れ忘れた
- 源泉徴収票に記載ミスがあった
- 医療費控除やふるさと納税を忘れていた
- 社会保険料控除(国民年金など)を入れ忘れた
手続き方法は?
更正の請求書を作成し、e-Tax、郵送、税務署の窓口への持参のいずれかで税務署へ提出します。
出典:令和6年分所得税及び復興特別所得税の更正の請求書|国税庁
e-Taxでは、確定申告書等作成コーナーの「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」から作成できます。画面の案内に従って入力を進めましょう。
手書きの場合は、「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続|国税庁」から該当年分の更正の請求書をダウンロードして記入します。
更正の請求には証拠書類が必要です。たとえば、必要経費の計上漏れがあった場合は領収書や請求書のコピー、社会保険料控除の申請漏れは国民年金保険料の支払い証明書などを添付しましょう。
ただし、請求書と必要書類を提出すれば、100%更正の請求が認められるわけではありません。税務署が審査をおこない、請求が認められれば、税金の還付手続きが進められます。審査には時間がかかるため、還付までには数ヵ月かかることもあります。
「更正の請求」手続きの期限は?
更正の請求期限は、確定申告書の提出期限から5年以内です。
たとえば、令和6年(2024年)分の確定申告は、令和12年(2030年)3月17日まで請求可能です。
- 確定申告書の提出期限:令和7年(2025年)3月17日
- 更正の請求書の提出期限:令和12年(2030年)3月17日
住民税はどうなる?
住民税も、後日お住まいの市区町村から連絡があります。住民税が戻ってきたり、これから払う住民税が安くなったりします。
申告期限「後」に少なく払っていたら「修正申告」
申告期限後に「本来よりも少ない税額を申告していた」と気づいた場合は、「修正申告」をおこない、不足分を正しく納めます。
たとえば、以下のような間違いに気づいた場合です。
- ・売上の計上漏れが判明した
- ・配偶者の年収を誤って認識し、配偶者控除を適用してしまった
- ・社会保険料を二重に控除していた
修正申告をおこなわずに放置すると、後から税務調査が入った際に「過少申告加算税」や「延滞税」が課される可能性があります。
また、税務調査は通常、過去3~5年分が対象ですが、悪質なケースだと判断されると最長7年に延びることがあります。リスクを避けるためにも、早めに修正申告をおこないましょう。
なお、延滞税や加算税などのペナルティは、「確定申告の間違いによる4つのペナルティ」で詳しく解説しています。ぜひあわせてご確認ください。
手続き方法は?
修正申告の流れは以下の通りです。
- 修正申告書を作成(本来の税額を正しく計算)
- 不足分の税金を納付(納付書を使用、または電子納税)
- 税務署へ提出(e-Taxまたは書面で提出)
修正申告は通常の確定申告と同じように申告書を作成し、修正内容を明示して提出します。
インターネット(e-Tax)、郵送、税務署の窓口への持参のいずれかで提出可能です。
e-Taxでは、確定申告書等作成コーナーの「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」から作成できます。画面の案内に従って入力を進めてください。
手書きの場合は、申告書の第一表に「修正申告」と記載し、種類欄で「修正」に〇をつけます。修正前の税額や修正後の増加額を記入しましょう。
出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁
各年分の確定申告の手引きは「確定申告に関する手引き等|国税庁」からご確認ください。
修正申告後の納税は?
修正申告により追加の税額が発生した場合、「修正申告書を提出した日」が納期限となります。そのため、修正申告書の提出と同時に、不足分の納付が必要です。納付が遅れるほど延滞税が増えてしまうため、早めに納付をしましょう。
確定申告間違い4つのペナルティ
確定申告でのミスや申告漏れがあると、以下の4つのペナルティが発生します。
- 払った税金が少なかったら「過少申告加算税」最大25%
- 確定申告していなかったら「無申告加算税」最大40%
- 悪質な脱税は「重加算税」最大50%
- 納付が遅れた分だけ「延滞税」
順番に解説します。
払った税金が少なかったら「過少申告加算税」最大25%
本来納めるべき税額よりも少なく申告していた場合、不足税額にたいして「過少申告加算税」が発生します。
過少申告加算税の税率は、以下のとおりです。
| 不足税額 | 50万円以下の部分 | 50万円超の部分 | |
| 税務調査の事前通知「前」 | 0%(ペナルティなし) | ||
| 税務調査の事前通知「後」 (調査前) | 5% | 10% | |
| 税務調査「後」 | 通常 | 10% | 15% |
| 税務調査で帳簿の提示なし等 | +10% | ||
自主的に修正申告をおこなった場合には、過少申告加算税はかかりません。
しかし、税務署から税務調査の通知があった後で修正申告をすると、過少申告加算税がかかります。
特に、令和6年1月1日以降は新たなルールが追加されたため、以下のケースではさらに税率が上がります。
| 追加される税率 | |
| 帳簿の提示を拒否した | 10% |
| 売上金額の記載が本来の2分の1未満だった | 10% |
| 売上金額の記載が本来の3分の2未満だった | 5% |
具体的な計算例で、確認しましょう。
①もともと30万円納税していたが、税務調査後に修正申告で70万円に増額(不足分40万円)
→40万円×10%=4万円(加算税)
②もともと30万円納税していたが、税務調査後に修正申告で100万円に増額(不足分70万円)
→50万円×10%+20万円×15%=8万円(加算税)
③もともと100万円納税していたが、修正申告で250万円に増額(不足分150万円)
→100万円×10%+50万円×15%=17万5,000円(加算税)
不足税額が大きいほど、過少申告加算税も高額になり、追加負担が増えます。
間違いに気づいたら、できるだけ早く修正申告をおこないましょう。
確定申告していなかったら「無申告加算税」最大40%
申告期限までに確定申告をしなかった場合は、「無申告加算税」がかかります。
無申告加算税率は、以下の通りです。
| 申告の時期 | 50万円以下 | 50万円超300万円以下 | 300万円超 | |
| 税務調査の事前通知「前」 | 5% | |||
| 税務調査の事前通知「後」 (調査前) | 10% | 15% | 25% | |
| 税務調査「後」 | 通常 | 15% | 20% | 30% |
| 繰り返し無申告だった場合等 | +10% | |||
| 帳簿の提示をしなかった場合等 | +5~10% | |||
自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税は5%です。
しかし、税務署から連絡があってから申告をした場合には、10%以上の無申告加算税がかかります。特に、無申告を繰り返している場合は、20〜40%にまで跳ね上がります。
税務署から指摘を受ける前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、申告漏れに気づいたら、できるだけ早く申告するようにしましょう。
悪質な脱税には「重加算税」最大50%
意図的に所得を隠したり、架空の経費を計上したりするなど、悪質な申告ミスが発覚した場合、通常の加算税よりも重い「重加算税」がかかります。
重加算税の税率は、以下の通りです。
| 通常 | 悪質な場合 | |
| 過少申告(税額を少なく申告していた) | 35% | 45% |
| 無申告(申告をしていなかった) | 40% | 50% |
特に、悪質なケースでは本来払う税額の1.5倍にもなる可能性があります。
税務署から指摘を受ける前に自主的に修正申告をおこなえば、重加算税ではなく通常の加算税(10〜15%)で済む可能性があります。不正な申告は大きなリスクを伴うため、正しく申告し、問題があれば早めに修正しましょう。
納付が遅れた分だけ「延滞税」
確定申告の期限までに税金を納付しなかった場合、「延滞税」が発生します。
延滞税は、納付が遅れた日数に応じて加算される利息のようなもので、納付が遅れるほど負担が大きくなります。
延滞税の税率(令和6年)は、以下の通りです。
- 納付期限から2ヵ月以内:2.4%
- 納付期限から2ヵ月超:8.7%
各年分の延滞税率は、「延滞税の割合|国税庁」でご確認ください。
ただし、追加で納付する税額が1万円未満だった場合や、延滞税の税額が1,000円未満だった場合には、延滞税はかかりません。
また、自主的に修正申告をおこなう場合、一定期間の延滞税を免除する特例が適用されることもあります。
納付が遅れた場合でも、できるだけ早く支払い延滞税の負担を最小限に抑えましょう。
確定申告間違いを防ぐ!よくある間違い例
確定申告では、多くの方が似たようなミスをしがちです。
次の5つのよくある間違えをあらかじめ把握して、確定申告ミスを防ぎましょう。
- 間違い①医療費控除の対象や計算方法をミス
- 間違い②ふるさと納税のワンストップ特例でミス
- 間違い③配偶者控除・扶養控除の適用ミス
- 間違い④住宅ローン控除の1年目に申告漏れ
- 間違い⑤副業・フリマアプリの収入申告漏れ
順番に解説します。
間違い①医療費控除の対象や計算方法
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の一部が軽減される制度ですが、申請ミスが多い控除のひとつです。
特に、以下のような間違いがよく見られます。
- 栄養ドリンクなど、予防や疲労回復のため費用を控除対象にしてしまう
- 予防接種費用を控除対象にしてしまう
- 美容目的の治療(ホワイトニングなど)を控除対象にしてしまう
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などを控除対象にしてしまう
- 高額療養費や出産育児一時金を差し引かずに申告してしまう
- 保険会社からの保険金を差し引かずに申告してしまう
- 家族全員分の医療費を合算し忘れる
適用条件をしっかり確認し、対象となる医療費だけを申告しましょう。
また、医療費控除の申請では領収書の提出は不要ですが、税務署からの問い合わせに備えて5年間の保存が必要です。
間違い②ふるさと納税のワンストップ特例
ふるさと納税を利用する際、「ワンストップ特例を使ったつもりが、結果的に適用されていなかった」ミスがよくあります。
特に、以下のような間違いが多いため、注意しましょう。
- ワンストップ特例の申請書を期限内に提出し忘れた
- 6つ以上の自治体に寄付した
- 確定申告をしたことで、ワンストップ特例が無効になった
申請書の提出期限は「寄付をした翌年の1月10日まで」です。これを過ぎると確定申告が必要になります。
ワンストップ特例利用できるのは「5自治体」までです。6自治体以上にふるさと納税した場合は確定申告が必要です。
また、ワンストップ特例申請書を提出期限内に提出しても、ふるさと納税以外の理由で確定申告をした場合、ワンストップ特例は適用されません。ふるさと納税分も含めて、確定申告が必要です。
確定申告の際は、以下の「寄付金控除欄」にふるさと納税の情報を記入し、寄付証明書もしっかりと保管しましょう。
出典:「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁」
間違い③配偶者控除・扶養控除の適用ミス
配偶者控除や扶養控除の申請で年収制限を誤解して申告するケースが多く見られます。
よくあるミスは以下の通りです。
- 配偶者や扶養親族の所得を正しく計算していない
- 本人の所得が1,000万円を超えていたが、配偶者控除を申請した
配偶者控除・扶養控除を申請する前に、収入状況の正確な確認が重要です。
| 合計所得金額 | 年齢 | 控除額 | |
| 配偶者控除 | 48万円以下 かつ、本人の所得1,000万円以下 | ー | 最高38万円 |
| 70歳以上 | 最高48万円 | ||
| 配偶者特別控除 | 48万円超〜133万円以下かつ、本人の所得1,000万円以下 | ー | 1~38万円 |
| 扶養控除 | 48万円以下 | 16歳以上 | 38万円 |
| 特定扶養控除 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | |
| 老人扶養控除 | 70歳以上 | 48万円(同居58万円) |
特に、以下の点に注意しましょう。
- 配偶者や扶養親族は「収入」ではなく「合計所得金額」で判断する
- 本人の所得が1,000万円を超えている場合、配偶者控除等は適用できない
- 扶養親族の年齢は「12月31日時点」で判断する
- 別居している親族でも、生計を一にしていれば扶養控除が適用されることがある
扶養控除・配偶者控除の申請ミスを防ぐため、事前に家族の収入や生計状況を確認し、正確な情報で申告しましょう。
間違い④住宅ローン控除の1年目
住宅ローン控除を受けるためには、1年目のみ確定申告が必要です。
しかし、以下のような勘違いで申告漏れが発生することがあります。
- 勤務先の年末調整だけで住宅ローン控除を受けられると思っていた
- 住宅取得に関する書類(登記事項証明書・借入金残高証明書など)を用意していなかった
1年目に確定申告をしないと控除を受けられないため、申請を忘れないようにしましょう。
間違い⑤副業・フリマアプリの収入申告漏れ
近年、副業やフリマアプリの利用が増えていますが、「収入が少ないから申告しなくても大丈夫」と勘違いし、確定申告をしないケースが増えています。
副業で得た所得(収入から経費を差し引いた金額)が年間20万円を超える場合、会社員であっても確定申告が必要です。
また、フリマアプリでの売上も不用品の売却は非課税ですが、仕入れをおこない転売している場合は課税対象です。
特に、近年税務署はインターネット取引に対する申告漏れのチェックを強化しています。「少額だから問題ない」と考えて放置していると、後で税務調査の対象となることもあるため、忘れずに申告しましょう。
よくある質問
確定申告でよくある質問と回答をまとめました。
- 確定申告が合っているか不安…
- 確定申告間違いは指摘されないこともある?
- 税務調査は何年前まで遡って調査される?
- 確定申告間違いの指摘はいつごろある?
確定申告が合っているか不安…どうしたらいい?
確定申告の内容に不安がある場合、次のいずれかの方法で事前にチェックしましょう。
- 税務署の無料相談窓口で確認する
- 税理士に依頼してチェックしてもらう
特に、控除や計算方法が正しいか不安な場合は、専門家に相談すると安心です。
確定申告間違いは指摘されないこともある?
確定申告で間違いがあっても、すべてのミスが税務署から指摘されるわけではありません。
申告書の内容だけでは誤りをすぐに特定できないこともあり、指摘されないケースもあります。
しかし、近年はマイナンバー制度やインボイス制度の導入、AIの活用によって、確定申告のミスは発覚しやすくなっています。
特に、AIの導入により、以下のような申告漏れのリスクが高いケースが重点的に調査されるようになりました。
- 申告書の不備が多い業種
- 現金取引が多い業種(飲食業や小売業など)
- 切りのよい金額で申告(売り上げや経費を10万円単位などで記載)
これにより、2024年所得税の追徴税額は過去最高を記録しています。
後から税務調査で発覚すると、追徴課税などのペナルティがかかる可能性があります。申告前にしっかりと内容を確認し、誤りがないようにしましょう。
税務調査は何年前まで遡って調査される?
通常、過去3~5年間分の税務調査がおこなわれます。
しかし、悪質な脱税が疑われる場合は、最大7年間まで遡って調査されることがあります。
特に意図的な申告漏れや虚偽の申告があると、長期間の調査対象となる可能性があるため、
適正な申告をおこないましょう。
確定申告間違いの指摘はいつごろある?
簡単な計算ミスや記載漏れは、比較的早い段階で連絡が来ることがあり、確定申告期間中に指摘されるケースもあります。
本格的な税務調査は、一般的に確定申告が終わった後の4〜5月頃や、7〜11月頃が多いといわれています。
税務署からの指摘を避けるためにも、確定申告の内容を事前にしっかり確認しましょう。
確定申告間違いは連絡がくる前に修正を!
確定申告のミスは、すぐに指摘されるものもあれば、税務署から連絡が来ないものもあります。
計算ミスや記載漏れは早い段階で通知されることがありますが、税金を多く払いすぎた場合などは、自分で気づいて対応しないと返金されません。
また、確定申告で誤りがあった場合、放置すると加算税・延滞税などペナルティが増えます。
ただし、自主的に修正申告をすると、ペナルティの負担を軽減できます。
本記事で解説した確定申告の間違いが指摘されるケース・されないケースを確認し、適切な対応をとって、税務リスクを最小限に抑えましょう。
申告内容に不安がある場合は、税務署や税理士への相談もおすすめです。
当事務所では単発でのご相談も承っております。
当事務所のサービスメニュー